|
|
「なあ。どっか行かないか?」
「はあ?」
田口はいつもの部屋で、いつもの書類の山に埋もれていた。そして、救命救急センターの将軍はいつものように、一人まったりと息抜きをしていた。
「お前のところはいつも忙しいだろうけど。うちだって、年度末でいろいろ大変なんだ」
「俺だって、いつも以上に大変だぞ。四月からの新規研修医の受け入れに、職員の異動に、来年度の予算確保に運営方針、あちこちからの苦情報告…。おまけに、評価も一気に押し寄せてきている。けど、患者は待ったなしだしな」
速水が定位置になったソファに寝転んでぼやく。どうやら、デスクワークが好きでない(できないわけではないところが、速水の速水たる所以だ)将軍は、山と積まれた事務仕事に根を上げかけているようだ。やれやれと、田口はため息をついた。
「行ってもいいけど、留守の間に貯まった仕事を後から片付けるのは嫌だなぁ。ただでさえ、ぎりぎり自転車操業だから、留守にした日には、二割どころか三割り増しで働かないと…。できるかなぁ」
オレンジのわがまま将軍と影で噂される速水が、現実逃避したくなるぐらいへたると、なかなか大変なのを知り尽くしている田口。これ以上、速水がへたれないよう言葉を選ぶ。
「確かに、お前はタンポポだからなぁ」
誉めているのか。貶しているのか。いまいち分からない速水にちょっと気分を害されつつも、田口は大人な態度で接する。
「だろう? でもって、俺が忙しくなると、帰宅時間は深夜になるし、時にはそのまま泊まるかもしれない。そうなったら、速水は家に帰っても一人と一匹だよなぁ。まあ、俺がいなくてもありすがいるからいいか。でも、ありすの世話をお前に託すのは不安だから、どうせなら、こっちに連れて来るか。そうすると、お前、本当に一人だぞ。もちろん、ありすが居ても、夜勤明けのゴミ出しも、風呂掃除も洗濯も電気釜のセットも、悪いけどひとりで頑張ってくれ…」
淡々と田口は事実を並べていく。わがまま将軍はプライベートでは田口にべったりで自己中だ。なので、このぐらい言わないと、後で嵐が吹き荒れる。ついでに、楽の後には苦があって、苦の後には楽がある…と思い出したように付け加えた。
「そんなに忙しいのか?」
「いや。お前ほどじゃないと思うけど。それなりにな。速水も忙しいなら、俺に遠慮せず、大学や病院に残って構わないから」
言外に田口は、俺はお前が居なくてもちっとも気にしていないし、逆に気楽でいいかもと匂わせる。と、速水ががばっと身体を起こした。
「お前が残るって言うんだったら、俺も残る。お前が家にいるのに、何で俺が当直とオンコール呼び出し以外で残ってなくちゃいけないんだよ」
「っていうか。両方残ったら、ありすはどうなるんだ? そうならないように、お前もこつこつ仕事を片付けろよ。春休みになったら、今より時間ができるとだろうから、また、弁当を作ってやるよ」
昨年のシルバーウィークに、五連休だった田口は日勤の速水ために、毎日、弁当を作ってやった。田口にしてみれば、多忙な速水に主夫している自分ができることをしたに過ぎなかった。しかし、速水にしてみれば、思いがけない出来事で毎日、上機嫌だったのは言うまでもない。
「いつ暇になる?」
「だから、春休み。それまでは提出書類に追われる日々が続く」
田口はデスクカレンダーを眺めつつ、速水を振り返った。
「25日が卒業式だろう。でもって、学期末休業が31日までだから、一週間はあるってことか」
速水もカレンダーを覗き込んで、確認をしていく。
「けど、その前に…、何かあったよなぁ。行灯…」
突然、速水は思い出したように田口の耳元で、意味深に呟いた。指は三月十四日を指している。世間で言うところの「ホワイト・デー」。イベント好きな速水をごまかせるとは思わなかった田口だが、できればスルーしたいが本音だった。
「ホワイト・デーか。すっかり、忘れていた…。スーパーのクッキー…じゃ、だめ…だよな」
ホワイト・デーのお返しで、毎年いろいろ悩む田口としては、速水をスルーできたらかなり楽になる。もっとも、去年はバレンタインにチョコを貰わなかったので、速水を無視していたら、ごねられて一悶着起きた。しかも、今年もバレンタインには田口からはチョコを渡したが、速水からは何も貰っていないので、田口的にはスルーしたいが本音だったりする。それでなくても、バレンタインに病棟の患者からいろいろ貰った田口としては、何かお返ししなくてはと思っている。
「それでもいいけどな。別にクッキーを食べたいわけじゃないからな。だから、裸エプロンでも、泡踊りでも、結婚式でも…、お前がくれるものなら何でもOKだ」
速水はにっこり流し目で田口に微笑んだ。対して、田口の顔は引き攣った。速水の希望は男なら一度はして貰いたいことばかりかもしれないが、自分がしてもらうのと、自分がするのでは天地ほどの差がある。
土下座して頼まれたって、絶対にするもんか。田口は固く心に誓う。
「ホワイト・デーで思い出したけど、今年の病棟のお返しは何にしよう。去年はお前のおかげで、あられは好評だったけど、結構。お金が掛かったし…」
「お前、何しみったれたことを言ってるんだ? 金の問題じゃないだろう? 相手が喜ぶことをするのが大事だろうが…」
速水が呆れたように、ため息混じりに呟いた。
「そうだけど。うん、まあ、忙しすぎて他を考える暇がないから、今年もあられでいいか」
田口にとって、ホワイト・デーは迷惑以外何ものでもなかった。年度末のくそ忙しい時期に、愛だの恋だの夢見ている暇はない。大学の教員はこの時期、新学期の準備と年度末の整理で寝る暇もないのが実情だ。教授の入れ替えがあれば、研究室の異動もあるし、院生の数によっては講座の入れ替えもある。それだけでなく、病院の方も診療日の入れ替えや、スタッフの異動がある。
だからと、ホワイト・デーのようなイベントを無視すると、人間関係にひびが入るのは目に見えている。ただでさえ、大学というところは陰謀渦巻くラビンスなのだ。せめて、波風建てないよう気を遣うのは、最低限の処女術と田口は知り尽くしている。なので、どれだけ面倒でも、馬鹿らしいと思っても、義理チョコにはきっちりお返しをするようにしていた。
問題は速水。外面は我が儘だが、それは患者のためなので、常に尊敬と畏敬の目で見られるスピードスター。しかし、田口の前では、どこのガキだというぐらい自由奔放に振る舞うのでたちが悪い。いい歳した男のそのな態度を、可愛いと言えば、可愛いのだけど…。
「俺は義理あられにするけど、速水は義理返しをどうするんだ? 俺はお遣いに行かないからな」
「うちのナースたちか…。やっぱり返さないと怒るよな」
「多分な。ちょっぴりお返しを期待するから、速水にやるんじゃないか? 何にしても、食べ物の恨みは怖いから気をつけろよ。そんなので、足元すくわれでもしたら、救命救急センター部長としては目も当てられない」
「確かに。まっ、俺も今年は去年と違う戦略を立ててはいるんだけどな」
田口にべったりくっついて、速水が田口のふわふわの髪にキスを落とす。それに何となーく嫌な予感がする田口だった。
「取りあえず、その戦略というのは聞いてやるけど、俺は手伝わないからな」
話だけは聞いてやるぞ、の強気な田口に速水は苦笑を漏らした。
「今年は市販のクッキー生地を型抜きして、オーブンで焼く。手抜き手作りクッキー作戦だ」
「ちょっと待て。それは誰がどこで作るんだ?」
田口の疑問はもっもともだ。
「あん? 俺が、家で作るに決まっているだろう。オレンジの合間に、そんなの作る暇が俺にあるはずないだろうが」
至極当然の速水に、田口は取りあえず、自力で作ろうと考えたのは評価すべきだろうか? それとも、巻き込まれるのが見え見えのこの状況にどう自分は対処すべきか。と真剣に考え始める。
「まあ。俺を巻き込まないでくれるなら、異論はないけど」
田口が消極的な反論を口にすると、将軍の目が寂しそうになった。それに田口はほだされて、俺も手伝ってやるよと言いそうになったが、今はぐっと飲み込んだ。周りが速水の我が儘を認めるのを、田口は良くもあり、悪くもあると思っている。なので、一人ぐらいは速水に反抗しないと、こいつはどこまでも他人と妥協しようとしなくなってしまうかもと、田口は懸念している。
「俺のお返しだから、行灯に作らせるわけにはいかないのぐらい分かっているって」
明るく断言する速水に、田口は頷くに止めた。
そして、3月14日。深夜から大忙しのオレンジ新棟一階に、夜勤スタッフが登場を待ちわびていた将軍が颯爽と姿を現した。相変わらず、無駄にいい男フェロモンをまき散らしながら、左手に小振りのカゴを持っていた。
「おはようございます。部長」
「ああ、おはよう」
おはようございます。と速水の姿に気づいたスタッフが次々と挨拶をする。それに速水は爽やかに返答する。
どうやら、今日のジェネラルはご機嫌麗しいようだ。と、当直を任せられていた医師たちはほっと胸をなで下ろした。この様子なら、朝一発目からチュッパチャップスが飛んでくることはなさそうだ。と、互いに目配せをする研修医たちだった。
昨夜の当直は、救命救急センターに所属する医師と小児科と脳外科からそれぞれ一名ずつ派遣された医師でまかなっていた。子どもと脳に関しては、オレンジに所属する医師がどれほど優秀でも、彼らの所属元が消化器外科、心臓外科、整形外科であるのを考えると、どうしても難しくなる。診断はできても、直ちに適切な処置を行わないと生命が危機にさらされてしまう。それが救命救急センターなのだ。以前は救急事例に対応した医師、それぞれの力量や経験などで救急患者を扱っていたが、今はJATECやACLSなどが普及し、全国どこでも同じような初期治療を受けられるようになった。だからこそ、専門医の存在は大きい。脳外科医の微細な脳内腫瘍の発見や小児科医の予後予想などは患者説明や予後に大きく影響する。
速水は足早にスタッフルームに入ると、広いテーブルに持って来たカゴを乗せた。そして、正面のボードに貼られた当直メンバーを確認した。その側を通り過ぎるスタッフは敢えて、カゴには興味を示さない。と言うのも、以前、同じように速水がフリル付きカゴを持って来たとき、中に入っていたのは、うさぎのありすだった。今回も、ありすかもしれない。と思うと、見て見ない振りに限る。非常に学習能力の高いスタッフでだった。
午前八時半になった。病棟に一斉放送のチャイムが鳴る。勤務開始である。看護師の申し送りが始まる。前後して、当直医師の報告が始まった。速水はボードに記入された重症患者の診断名を見る。瞬時に報告内容と合わせて、今後の治療方針や経過などを考える。
看護師の申し送りは、ICUに送った患者とオレンジ一階で管理している患者になるため長い。それに比べると、医師の報告は短いが、処置者が多ければ、それだけ、報告が多くなる。しかも、重症患者の治療経過やこれからの様子などの予想なども伝えられるので、ほんの少しの息抜きもできない。次の患者が来たら、誰を上に上げるか。瞬時に判断する能力が救命救急センターの医師には必要なのだ。
「…。当直スタッフはお疲れだったな。オフの者はゆっくり休んでくれ。そして、日勤組は気合いを入れて行こうか」
夜間報告を受けた速水の言葉に、日勤の医師たちは椅子から立ち上がり、それぞれの持ち場へと姿を消した。それを見送った速水は大きなあくびを一つ漏らした。ついでに、コキコキと肩を動かした。
「速水先生。先生も人間だったんですね」
後期研修医の山下だった。
「あん? 山下ぁ、お前、俺をなんだと思ってるんだ?」
「えっと…。スーパードクター…ですか」
「あのなぁ。俺はロボットじゃないから、疲れもするし、屁もこく。時にはへたれるし、愚痴もぼやく。そのな姿は患者の前では絶対に見せないがな」
にやりと笑う顔はいたずらっ子のようで、山下はぽかんとその美貌に見とれる。それに速水は苦笑。そして、
「おい、戦闘開始だぞ、研修医。俺を眺める暇があるなら、患者を診てこい!」
と尻を叩く。慌てて出て行く後ろ姿を見送る速水は、男に見つめられても嬉しくないとか、お前、彼女いないのかとか、内心で呟く。が、そんな若さが速水は嫌いではない。振り返れば、自分にもそんな時代があったのだから…。
俺らが外科医になった頃と比べると、救命の現場格段に効率が上がり、ハード面では整備された。しかし、相変わらず、脳卒中も心停止も減っていない。交通事故もだ。死者は減ったと報道されるが、それは事故件数が減ったためか、医療技術の向上で減ったのか、はっきりと分からない。もちろん、昔に比べれば、車の数も増えているので、事故が増えるのは単純に分かる。が、ずっと救急センターで働いている速水にしてみれば、数自体は変わらないように思えた。
しかも、最近は虐待というものも存在する。桜宮ではあまり遭遇しないが、大都市では小児虐待、DV、老人虐待などがあり、事件に巻き込まれた患者も多く搬送されると聞いている。自殺者も増えた。
やりきれないと思うこともある。それでも、死と戦うのは、元気に病院を退院する患者の笑顔を見るためだと思う。大学病院の救命救急センターなので、三次外傷はすべて受け入れている。ここでスペシャリストの医師たちが消えゆく命をつなぎ止めている。赤字量産部署と悪名が経営陣からは囁かれているが、ここがなければ、待ったなしの患者は助からない。それに国も気づき始めたし、大学の医学部も取り組み始めた。
救急医療の未来は、ちょっとは開けたかな。
速水はテーブルに頬杖をついて、行き交うスタッフを眺めた。滅多にこんなゆっくりした時間が取れない速水は、職員の動線などを中心にチェックする。
「速水部長。どうされたのですか?」
「ああ。師長か。いや、うちのスタッフは頼もしいなぁと眺めていた。ああ、そうだ。これ、バレンタインのお返しだ」
フリルのついた可愛いバスケットを速水は、花房師長に差し出した。
「まあ。ありがとうございます。後で、みんなにお披露目しますね」
「そんなたいそうなものじゃない。俺が型抜きをして、焼いた奴だから、味だけは保証する。生地はプロが作ったものだからな」
「部長が…作られたの…ですか?」
花房の目が大きく見開かれた。そりゃそうだろう。救命救急センタートップ、待遇は教授レベルの速水が、しかも、俺様ジェネラルが自らホワイトデーのクッキーを焼いてくるなど、考えたこともないはずである。今までは某百貨店のロゴ入り、有名クッキーメーカーのものが定番だったのだ。
「違う。型抜きをして焼いただけだ。そんなわけで、疲れた。田口の奴はシンデレラ・タイムになった途端、“おやすみ~”って寝やがるから、ひとり黙々とオーブンで焼いたって訳だ。まあ、次はないな」
仕事どころか、田口にも相手にされなかった行動に対して、将軍のモチベーションは常に低い。義理で頑張ったけど、もう二度としないという態度が見え見えだった。
「それでしたら、なお、皆で分けなくてはいけませんね」
花房はにっこり、感謝の笑顔を速水に向けた。
「はいはい。文句は受け付けないのでよろしく」
そう告げて、速水は部長室に逃げた。これ以上、この件について追求されてはたまらない。どうして、今回に限って、自分で作ってみようと思ったのかとか、どこの生地を選んだのかとか。単なる思いつきだったでは終わらない気がして、早々に退散した。
どっしりした椅子に座って、壁に設置されたモニターを見る。変化はない。
ふと、今頃、田口もあられを配っているのだろうなと思う。田口とあられとお茶…。似合いすぎて笑いたくなる。それに、縁側と猫が居れば完璧だ。似合いすぎて笑えない速水。
久しぶりに田口の実家に行ってみようか。速水は先ほどから目に浮かぶ田口と縁側と猫の光景に、ふっと思いついた。
桜宮市で育った田口には、まだまだ元気な両親が暮らす家がある。祖父母が建てたという家は、和風建築のどっしりとしたたたずまいで、修理をしながら、大切にされたいる。広い日本庭園には築山があり、池には鯉が優雅に泳ぎ、広い縁側がある。学生時代、お袋の味が恋しくなると田口には内緒で訪ねたものだった。速水が田口の作る料理が好きなのは、この母の味を感じられるからかもしれなかった。田口と恋人同士になるのでは頻回に通っていた敷居である。遠慮はないが、やはり、田口を組み敷いている身としては少しばかり肩身が狭い。それでも、田口よりは頻回に顔を出しているに違いない。
田口の母親は時々速水にメールをくれる。“おいしい魚をもらったから、お裾分け”とか、“お父さんがおいしい日本酒をいただいたので、飲みに来ない?”とか、“もうすぐ誕生日でしょうから、ちらし寿司を作ったら、食べる?”など。たいていは食事の誘いだ。比較的暇そうな息子ですら、食事がままならないとぼやいているのを知っているだけに、救命救急センターの速水はもっと大変だろうという心遣いだった。速水は都合がつくときは、取りあえず、田口にも声を掛けて顔を出すようにしていた。しかし、呼ばれたのが速水だけというのも結構あったりする。
旅行に行くのは面倒だから、田口んちに帰ろう。そんでもって、しばらくのんびりしよう。
「あっ、田口? 俺だけど、しばらく、お前の実家に帰るわ。しばらく、そこから通勤するから、お前もこっちに帰れよ」
思いついたら即行動。内線電話の向こう側で、田口がなんなんだと慌てていた。そんなの気にせず、速水は“あっそうだ。取りあえず、ありすも連れて行くから、お前も来いよ”と告げて切った。続けて、田口母にメールを送る。当然、田口は無視。
というわけで、本日の仕事にもいつも以上の気合いが入る将軍だった。
慌てたのは田口。愚痴外来が終わると同時に、絶対に足を踏み入れたくないオレンジにやって来た。
「速水! お前どうしたんだ?」
周りを見ずに、田口は一直線に部長室に飛び込んだ。
「何が?」
速水は重厚なデスクの前に座って、事務処理に励んでいた。
「何かへまをしたのか? 謹慎…とか貰った訳じゃないよな。だったら、兵藤が黙っていないはず…。…後は、うちで何かあったとか…」
走ってきた田口が矢継ぎ早に言葉を重ねてくる。
「まあ、落ち着け、行灯。俺にもお前んちにも変化はない」
速水はちょいちょいと田口を手招いて、微笑んだ。こいつは俺が家族ごっこをしたがっているって、何で気づかないのかなぁ。と、ちょっとだけ悲しくなる。これで愚痴外来を任されているのだから、世の中は理解できない。
「じゃあ、どうしたんだ? うちの母親に脅されたとか?」
「あのなぁ。お前は何でそんなに悪い方に考えるんだ? お袋の味に浸りたくなっただけだって、思わないのか?」
「…速水なのに?」
「速水晃一だからだ。何か…、時々、俺はお前の家族に同情してしまうぞ。親孝行、しようと思った時には親はなし。いつまでも、あると思うな親と金。名言だなあ」
絶句する田口。だが、日々、消えゆく命と戦う速水にとっては、これは嘘でも冗談でもない。が、自分だけは違うと思いたいのも事実だと分かっている。
「分かった。俺も帰ればいいんだろう」
田口は内心のため息を殺して頷いた。速水が来ると家中大騒ぎになる。恒例の速水を囲んでの○○パーティーが連日開かれて、飲んだくれが量産されるのだ。何十年たっても、田口家では速水は大歓迎される。特に母親は速水を見て、頬を赤らめていたりするから困ったものだと思っている。
「その方が両親ともに喜ばれるに決まっているだろう」
当然だと言わんばかりの速水に、田口は複雑な顔を見せた。速水の家族はどう思っているのか知らないが、少なくとも田口は、自分の両親に速水との関係を告げたことはない。しかし、そこは親の勘でしょっちゅう入り浸る速水に感じるものがあるように思えて、なかなか足が向けられない。が、正直な思いだったりする。速水との関係は恥ずべきことではないと理解していても、親を悲しませているという後ろめたさはどうしても拭えずにいる。親が自慢できない息子は、やっぱり肩身が狭いと思ってしまうのは仕方ないかも…。
その辺に関しては、少々、日本人離れした考えの速水ほうが強い。一種、居直りのようにも思えるが、こんな俺を受け入れなくても認めろ、と真っ直ぐ顔を上げて相手と向き合う。感情と理性を分けて考える速水を、もっと見習わなくてはと思うときが増えてきた。だが、自分がその場面に遭遇したら、速水のようにできるかと言ったら、やっぱりできないだろうと田口は思った。
「…明日帰るって、連絡しておく…」
渋々、田口は返事をすると、もうここには用はないと帰ろうとした。それを引き留めようとした速水だったが、田口へ伸ばした手をそのままに、ランプに目を向けた。直後、赤くランプが点灯し始める。
「部長。交通事故、多発外傷患者三名搬送です」
「分かった。直ぐに行く。じゃあな」
そう田口に告げると、速水は白衣を手に前線へと向かった。
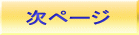
Copyright©2012 Luna,All Rights Reserved |
|